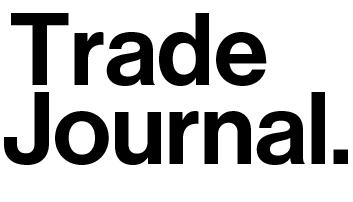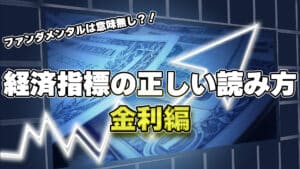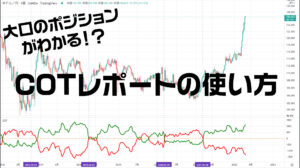RSIは一本のラインで表示され知名度の高いオシレーター系インジケーターです。
今回は、RSIの使い方について詳しく解説していきます。
RSIとは
RSIとは、JWワイルダー氏が開発したオシレーター系インジケーターで、「Relative Strength Index(リレーティブ・ストレングス・インデックス)」という言葉の略語で、日本語に約すと「相対力指数」と言います。
日本語に訳すと逆にわかりづらいですが、簡単に言い直すと、いまの相場が自分で決めた期間の相場と比べて、強いのか弱いのかを判断するインジケーターとなっています。強さを相対的に図るから、相対力指数と言うんですね。
RSIのパラメーター設定
RSIの設定値は初期値では14が採用されています。開発者のワイルダー氏が研究によって、あらゆるものには28日間の周期性があるということから、その半分の「14日間」が初期値として設定されています。
多くの人がそのまま初期設定の14で設定しているため、特別な理由がないかぎりは初期設定のままで問題ありません。
RSIの計算式
RSIの計算式は、
$$\frac {(14日間の上昇幅の合計)}{(14日間の上昇幅の合計)+(14日間の下落幅の合計)}✕100$$
となっています。
つまり、14日間の値動きを、上昇と下落の2つに分け、上昇が全体の何%だったかを計算しています。
例えば、14日間の上昇幅が100円で、下落幅が80円とすると、$$\frac {(100)}{(100+80)}✕100=55.5%$$となり、RSIの値は55.5%と表示されます。
RSIの見方
買われすぎ売られすぎ
RSIを見ることで、現在の相場が買われすぎなのか売られすぎなのかを確認することができます。
70~100%が買われすぎゾーンで、0~30%が売られすぎゾーンと呼ばれます。
Tradingviewで表示すると、30~70%に色がついています。

70~100%ゾーンにラインが存在すると、買われすぎと判断され売りサインとなります

RSIの弱点
単一のラインでわかりやすいシグナルを表示するRSIですが、弱点があります。画像からわかるように強いトレンドが出てしまうと、買われすぎゾーンにいるのにチャートはぐんぐん上昇してしまいます。
買われすぎというのは、適正値より高くてもみんながロングしている状態。ともとれるので価格が上昇しつづけてしまいます。
このダマシを減らすためには、他インジケーターと組み合わせ使うと良いでしょう。詳細については次章で説明します。

ダイバージェンス
RSIではダイバージェンスを確認することできます。ダイバージェンスとは、「チャートは高値・安値更新をしているのに、オシレーターは更新できていない」もしくは「チャートは高値・安値更新していないのに、オシレーターは更新している」現象を言います。

上昇トレンド中にダイバージェンスが発生した場合は、売りシグナル
下降トレンド中にダイバージェンスが発生した場合は、買いシグナル
となります。
RSIのダマシを減らす方法
前項でRSIを単独で利用すると、トレンド発生時にダマシが生じてしまうことを説明しました。
ダマシを極力へらすためには他のインジケーターと組み合わせて分析を行いましょう。
RSI+ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドと組み合わせることにより環境認識を同時に行うことができます。
ボリンジャーバンドの+1σより上に価格がある場合は、上昇トレンド。
ボリンジャーバンドの-1σより下に価格がある場合は、下降トレンド。
と環境認識を組み合わせることにより、赤丸ポイントのように、RSIでは買われすぎ、ボリンジャーバンドでは上昇トレンドというシグナルによって、RSIのダマシをへらすことが可能です。

RSIのまとめ
- RSIとは今の相場が買われすぎか売られすぎかを判断するツール
- 一般的に、買われすぎは売りサイン、売られすぎは買いサイン
- トレンド発生時にはダマシが発生してしまう
- ダマシを減らすには、他インジケーターとの併用を考える